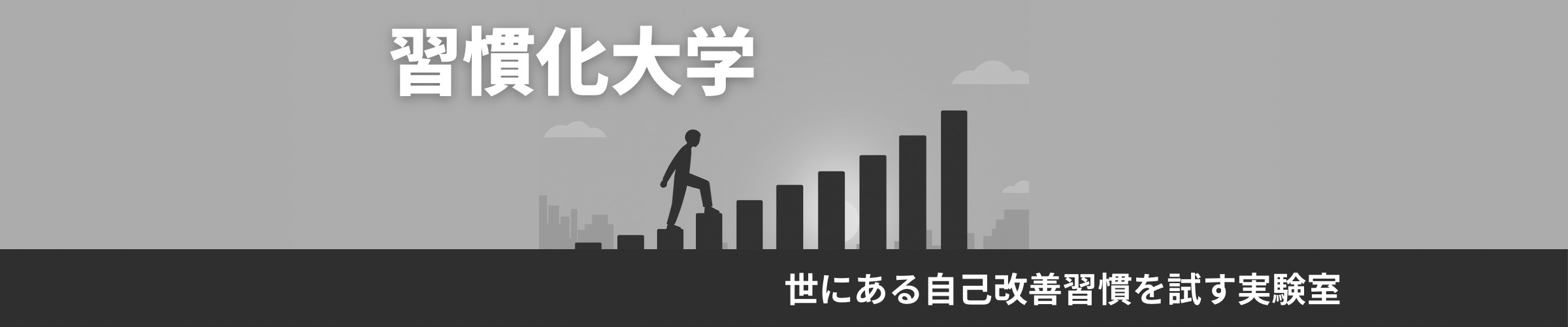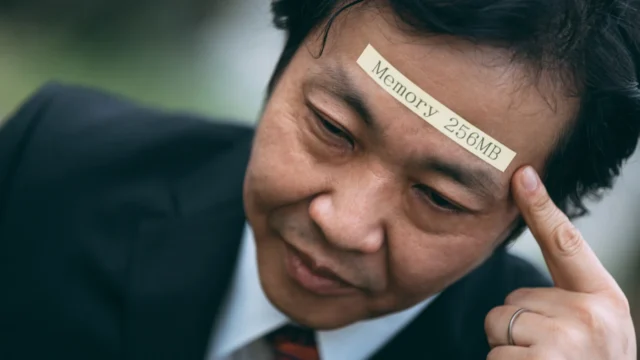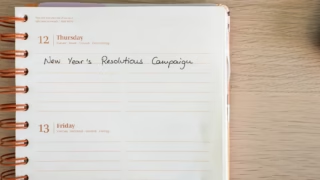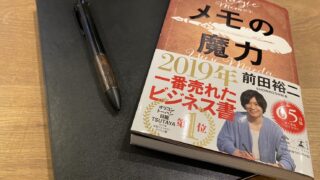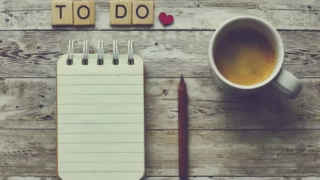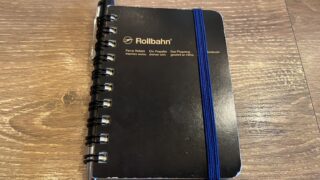はじめまして!
習慣化プロデューサーのえだちんです。
私は教育大学出身で、現在は人材育成会社で研修講師、組織の習慣化コンサルティングに従事している。
習慣化大学ではえだちんの学びや実体験を基に、人生を変える習慣や習慣化のコツをお届けしていく。
今回は「【習慣化】人生を変える習慣化4Step」ついて書いていく。
「続けられるのは意志力のある人だけでしょ」と思った人もいるかもしれない。
習慣化には確かに意志力がある人のほうが有利であるかもしれない。
ただ、意志力がない方が習慣化を仕組化するチャンスでもある。
習慣のメカニズムを知り、習慣化の4Stepを知ることで小さな意志力によって続けることができるようになる。
このブログでは様々な良習慣を紹介しているが、それらの良習慣を身に付けるための土台となる習慣化4Stepを紹介していく。
この記事では以下の人に読んでもらいたい。
・続けたいことがあるが、どうやったら続けられるようになるかが分からない
・ある程度続けることはできるが、改めて習慣のメカニズムを知りたい
・今まであまり、続けられたことがないので自分は「続けられない人」だと思っている
・習慣化は人生を変えるために必要かもしれないと思っている
習慣の力は偉大だ。
どんな成果にも、成功にも必ず「続ける」というプロセスが必要になる。
人生は一発逆転はほとんどない。
小さな努力を積み重ねた者が得たいものを手に入れる。
自己紹介も兼ねて私が続けてきたものを紹介する
- 日記(10年日記)5年以上(2020~2025[現在])
- ゼロ秒思考 6年以上(2019~2025[現在])
- 読書 300冊以上 6年以上(2019~2025[現在])
- 家計簿記録(Zaim) 6年以上
私の実体験、書籍や研究などを基に、習慣化4Stepを紹介していく。
人生を変える習慣化4Step

人生を変える習慣化4Stepは何か?
その結論から伝えよう。
①きっかけ(トリガー)の明確化
②行動のスモールステップ化
③報酬の明確化
④繰り返しによる固定化(習慣化)
きっかけによって行動したいという欲求が生まれ、行動する。
行動によって報酬を得ることができ、また行動したいと思う。
きっかけ→行動→報酬のサイクルが繰り返されることによって、習慣化する。
一つ一つ解説していく。
①きっかけ(トリガー)の明確化
きっかけ(トリガー)が脳に行動を引き起こさせる。
きっかけ(トリガー)とは報酬を予測させるわずかな情報である。
人が行動する時には必ず、何かしらの報酬(メリット)があるときである。
何気ない行動にも深堀っていくと報酬(メリット)がある。
我々の祖先は食物、水、セックスの相手など生存や繁殖などの原始的な報酬の在り処を示すきっかけに注意を払っていたのである。
現代では金や名声、権力や地位、賞賛や承認、恋や友情、個人的な満足という報酬を予測させるきっかけを求めている。
行動には必ずきっかけ(トリガー)がある。
そして、その「きっかけ(トリガー)」と「行動(Step②)」、そして「報酬(Step③)」が結びつき、繰り返されると習慣になる。
習慣の一番最初はきっかけ(トリガー)である。
きっかけ(トリガー)とは?

きっかけ(トリガー)とは習慣を忘れないようにするサイン、習慣(報酬)に気づくことである。
きっかけは行動を起こさせるものであると伝えたが、まだそこまでイメージしづらいかもしれない。
きっかけによって報酬に気づき、欲求を生み出し、行動の動機となる。
具体的に見ていこう。
- 歯を磨く習慣
①ご飯を食べた後、洗面所に行く(きっかけ)
②歯を磨く(行動)
③口の中がすっきりする。きれいになる(報酬) - テレビを見る習慣
①家に帰ってソファに座る(きっかけ)
②テレビをつける。テレビを見る(行動)
③面白いテレビ番組を見て満足する(報酬) - 読書する習慣
①寝る前にベッド入った時(きっかけ)
②本を手に取る(行動)
③本を読んだ達成感、本を内容を知れた喜び(報酬)
このようにこれを見ているあなたがしている何気ない習慣にもきっかけがある。
そしてそのきっかけによって、行動し、習慣化されている。
つまり、きっかけがないと行動は引き起こされないし、習慣化もされないのだ。
きっかけ(トリガー)を明確にするやり方

きっかけ(トリガー)を明確にするとは「タイミング」と「場所」を決めることである。
もっと言うと「いつ」「どこで」「何を」するのかを決めることだ。
いつ、どこで新しい習慣を行うのかを明確に決めている人はその習慣をやり通す可能性が高い。
一方、続けられない人、習慣にすることが苦手な人はいつ、どこで、何をするのかがたいていはっきりしていないのである。
タイミングを決める
このパートのポイントは時間ではなく、タイミングを決めるということである。
いつやるかとは時間ではなく、どのタイミングで行動をするかを決めることである。
時間単独ではきっかけ(トリガー)になりづらい。
(もちろん大まかな時間を設定することは重要であるが…)
時間で設定しても人はずっと時間を見ているわけではないし、刻一刻と時間は過ぎてしまうので時間が来ても忘れてしまったり、時間が来ていることに気付かなかったりするためだ。
ではタイミングとは何を決めればよいのか?
それは「○○の習慣(今ある習慣)をした後に△△の習慣(新しい習慣)をする」ことを決めることである。
上記には時間も含まれるが、時間を決めることは本質ではない。
現在の習慣と結びつけることこそがタイミングを決めることである。
新しい習慣を身に付ける最善の方法は毎日行っている現在の習慣に新しい習慣を結びつけることである。
例えば私は新しい習慣を身に付ける際、以下のように結び付けている。
- 朝起きて日光を浴びたら(現在の習慣)ベッドメイキングをする(新しい習慣)
- 帰宅後、夜ご飯を食べたら(現在の習慣)、体幹トレーニングをする(新しい習慣)
- 体幹トレーニングをしたら(現在の習慣)、読書をする(新しい習慣)
- 寝る準備をしてベッドに入ったら(現在の習慣)、読書をする(新しい習慣)
- カフェから会社に移動する時(現在の習慣)、
Audible(聴く読書)を聴く(新しい習慣)
コツは身に付けたい新しい習慣をすでに行っている習慣と結びつけることだ。
これらの習慣を結び付けていくことによって習慣の塊を作り出すこともできる。
新しい習慣を現在の習慣に結びつける方法はタイミングだけではなく、場所も習慣の中に自然と組み込まれる。
注意点として新しく行いたい習慣と同じくらいの頻度がきっかけにも必要である。
毎日行う新しい習慣を週1回しか行わない現在の習慣と結びつけては習慣化されにくい。
毎日行う新しい習慣には毎日行う現在の習慣と結びつける必要があるのだ。
今一度、毎日欠かさずに行う現在の習慣をリストアップしてみよう。
その中からどの習慣に結びつけるとよいか考えてみよう。
新しい習慣(身に付けたい習慣)が具体的なきっかけと結びついているほど、行う時間が来たことに気づきやすくなるのだ。
場所を決める(環境作り)

場所を決めるとは新しい習慣をどこでやるかを決めることである。
ポイントは家やこの部屋という粒度ではなく、この机やソファ、ベッドなどより詳細な場所を設定することである。
もっと言うとその場所にある「もの」と結びつけるとなおいい。
環境によって人間の行動は作られている。
自らの意思で行っている行動や習慣も実は環境によって引き起こされているのだ。
つまり、どこでやるかを決めること、環境を整えることによって行動や習慣を作り出すことができるのである。
どこでやるかを決める
新しい習慣を作り出す最初の段階ではより具体的な場所、もっと言うと「もの」と結びつけることが大切である。
行動は環境にあるもので決まるのではなく、ものとの関係で決まる。
具体的には家や会社という場所の環境ではなく、ソファやベッド、この机や椅子といったものとの関係性によって行動が習慣化される。
例えば、ある人にとってはソファは毎晩1時間本を読む場所であるが、他の人とっては仕事の後でテレビを見ながらアイスクリームを食べる場所かもしれない。
つまりは行動ともの(環境にある特定の場所やもの)を結びつけることで習慣を作り出す上でのきっかけとなる。
結びつける上での注意点としてはすでに習慣とものが結びついているところに新しい習慣とものを結びつけるのは難しいということだ。
ソファでテレビを見ながらアイスクリームを食べるという習慣がある状態からソファで読書をするように行動とものを結びつけてもうまくいかない。
すでにそこには行動とものの結びつきによる習慣があるからだ。
大切なのは新しい習慣と新しいもの(環境にある特定の場所やもの)を結びつけることだ。
そして、一つの行動には一つのものを結びつけることが大切だ。
環境を作る
どこでやるかを決めることと同時に行動しやすい環境を作り出すことも重要である。
行動しやすい環境を作るためには以下ポイントを押さえることである。
①行動を起こしやすい準備がされている
②複数のきっかけがある
例えば
- 夜ベッドで読書をしたいなら、枕元に本を置いておく
- 毎日ストレッチをしたいならストレッチする場所にマットを敷いておく
- もっとギターの練習をしたいならリビングにギタースタンドの上にギターを置いておく
これらによって、枕元の本を見るたびに読書しようとなるし、マットを見るたびにストレッチしないととなるし、リビングにあるギターを見るたびにギターを弾こうかなとなる。
行動を起こしやすい準備とともに複数のきかっかけとなるのだ。
習慣化したいなら引き金(トリガー)となるものを周囲に散りばめることで見るたびにその習慣のことを思い出し、考えていられるだろう。
他人によって作られた環境に生きるのはやめよう。
自ら環境を作り出し、習慣をデザインしよう。
私の好きな言葉を紹介する。
「環境が人を作り、人が環境を作る」
環境は作り出すことができる。
その環境によって習慣を生み出すこともできるのだ。
②行動のスモールステップ化
習慣を身に付けるためには「行動」しなければならない。
習慣は計画することでも、準備することでも身につかない。
習慣を身に付けたいなら小さな行動を行い、それを繰り返すことである。
つまり、このパートでは行動のスモールステップ化によって、行動のハードルを下げ、続けやすくすことである。
習慣は時間ではなく、頻度によって身につくのだ。
行動のスモールステップ化とは?

行動のスモールステップ化とは行動を簡単にすること、行動しやすくすることである。
当たり前だが、必要とするエネルギーが少ない簡単な習慣ほど行動しやすくなる。
そして、簡単な行動のほうがやる気になるのである。
習慣が難しいほど大きな抵抗を感じて、行動に移しにくくなる。
だからこそ、したくないときでも行動できるよう、行動が簡単にすることが大切だ。
行動のスモールステップ化のやり方
行動のスモールステップ化においては行動を簡単にすること、行動しやすくすることであるが、具体的には2つある。
・環境作り(行動を起こしやすくする準備)
・2分間ルール
環境作り(行動を起こしやすくする準備)

環境作りについては「①きっかけ(トリガー)の明確化」でも見たが、これは行動のスモールステップ化においても非常に効果的である。
習慣における行動を起こす上での抵抗を減らすのに最も効果的な方法は「環境作り」である。
私たちは抵抗の多い環境で始めようとすることがあまりにも多い。
例えば
- (漫画やテレビ、ベッドなど)誘惑だらけの家の中で集中して仕事をしようとする
- 気が散るコンテンツでいっぱいのスマホを使いながら集中しようとする
- 友人と夕食に出かけながら厳しいダイエットをしようとする
- お菓子やジュース、甘味などのストックがたくさんある環境でダイエットする
このように非常に抵抗が大きく、行動するのに大きな意志力を要する環境で行動しようとしている人が意外と多い。
大切なのはできるだけ良い行動がしやすい環境を作ることである。
例えば
- 運動したいなら、トレーニングウェア、シューズ、水筒を用意しておく
- 食事を改善したいなら、週末にたくさんの果物と野菜を細かく切って、容器に詰めておく
- ダイエットしたいなら、ジュースやお菓子、カップラーメンを誰かにあげるか、捨てるかして処分する
抵抗が小さいほど行動に起こしやすい。抵抗が大きいほど行動を起こしにくい。
極めてシンプルだ。
抵抗を小さくして行動を起こしやすい環境を作り出そう。
「①きっかけ(トリガー)の明確化の場所を決める(環境作り)」を見てもらいたい。
2分間ルール

2分間ルールとは「新しい習慣を始めるときには2分以内にできるものにする」というルールだ。
人は一度、行為を始めると想定よりも続けてしまう。
これは作業興奮といい、ドーパミンが出るためである。
例えば
- スナック菓子を少しだけ食べようと思ったらすべて食べてしまった
- 少しだけスマホを見ようと思ったら20~30分見てしまっていた
- ジムに行くのがめんどくさかったけど、行ったら1時間くらいトレーニングしていた
とはいえ、たくさんやることを前提に2分間ルールを設定するわけではない。
本当に2分間でやめてもいいのだ。むしろ最初はそれでいい。
人は小さく始めるべきだと分かっていてもつい、大きく始めてしまうものである。
特に始めようと意気込んでいるときほど、多すぎることを早すぎる時期にしたくなる。
どんな習慣も細分化すれば2分間バージョンに短縮することができる。
- 「毎晩寝る前に読書する」は「毎晩寝る前に1ページ読む」に
- 「毎日3キロ走る」は「ランニングシューズの靴ひもを結ぶ」に
- 「毎朝、朝活をする」は「毎朝、カフェに行く」に
- 「毎日、日記を書く」は「毎日、1行だけ日記を書く」に
たとえ後に続く行動が大変だったとしても最初の2分間は簡単であるべきである。
行動のハードルは限りなく低くすることがカギだ。
とにかく大切なのは「入り口の習慣」を設定することである。
「こんな2分間の習慣じゃ意味ない」「効果がないのではないか」と思う人もいるだろう。
ただ、大事なのは何かを行うことよりも習慣が現れるようにすることである。
最初の一歩を踏み出すことが何より大切なのである。
習慣が決まったタイミングで現れることで、きっかけと行動が結びつくようになるのだ。
③報酬の明確化
行動した後には報酬である。
報酬によって行動する際の欲求が生まれ、「またやりたい」と感じるようになる。
行動に対して欲求が生まれ、それらが繰り返されることで習慣が形成されていくのだ。
報酬によって、行動が魅力的になり、行動が満足できるものになる。
つまり、報酬は習慣における縁の下の力持ちである。
水面化であなたの習慣形成を支えてくれるものだ。
報酬とは?

報酬は行動する前に行動したいという欲求を生み出し、行動した後に満足し、また行動したいという欲求を生み出すものである。
報酬がなければ、行動したいと思いづらい、繰り返したいと思いにくくなるのだ。
報酬によっては人は動かされている。
報酬をうまく利用することによって行動を繰り返す確率を高めることができる。
より本能に根付いた報酬であればあるほど、習慣になりやすい。
例えば
- 食欲:食物と水を手に入れる
- 性欲(繁殖):恋人を見つけて、子供を作る(セックス)
- 睡眠欲:体を休める、エネルギーを節約する
- 承認欲:社会的に承認される、地位や名声を獲得する
- 社会的欲求:他人とつながり、絆を深める
上記のような人間が自然に持つ潜在的動機が報酬であるほど、報酬として大きな効果を発揮する。
報酬を予測した時、報酬を受け取った時にはドーパミンが分泌される。
我々を突き動かすのは報酬の予測と報酬の実現なのである。
報酬の明確化のやり方
報酬の明確化では具体的なやり方として2つある。
・習慣の記録
・ご褒美習慣との抱き合わせ
習慣の記録

習慣の記録とはカレンダーや手帳に習慣を実行した日を印をつけることである。
報酬は人間の本能に根付いた欲求に必ずしもフィットした形での報酬を設定することは難しいかもしれない。
応用が利きやすく、簡単に作り出しやすい報酬として「得たい状態を得ている感覚」が一つ報酬になりうる。
例えば
- 学校の課題が終わるたびに先生からシールやスタンプをもらうことができるため、必死になって課題をやる
- 体重計に毎日乗っていると少しづつ体重が減っているのが目に見えるので、ダイエットへの成果を感じられた
- 行きつけの店のスタンプカードが溜まるたびに嬉しくなった
このように目に見えるものでその量を測ると進歩した証拠が見ることができ、達成感が得られる。
その証拠が得たい状態を得ている感覚に繋がり、記録すること自体が報酬となるのだ。
つまり、習慣を行ったかどうか記録する方法はより良い報酬となる。
具体的なやり方はシンプルで以下が挙げられる。
・ノートに書く
・手帳に書く
・日記に書く
・スマホアプリに記録する
私は以下を記録している。
・1日の中で行ったことすべてを手帳に記入する
・睡眠時間(起床時間、就寝時間)をヘルスアプリに記録する
・日記に日常の気づきや学びを記入する
・1日の終わりに感謝を記入する
・朝活としてカフェに行った時間を記録する
・1日の中で食べたものを手帳に記入する
・体重をアプリに記録する
・今日行うタスクを書き出し、終わったら線で消す
┗手帳にもタスクを書き出し、進捗を記録する
などである。
正直まだまだあるが、記録することは習慣を身に付ける上で大きな味方となる。
ご褒美行動との抱き合わせ

ご褒美行動との抱き合わせとは「自分がしたい行動(ご褒美行動)」と「しなければならない行動(習慣化したい行動)」をセットにすることである。
<習慣化したい行動>をしたら<自分がしたい行動>をする。
当たり前であるが、自分の好きなことと同時に行えば習慣が魅力的になりやすい。
そして、その習慣を行うことによる報酬も明確になる。
例えば
- 読書2分間だけしたら、SNSを見る
- ネットフリックスを見ながらサイクリングマシンを漕ぐ
- ジムに行ったら仲のいい友達や綺麗な女性(かっこいい男性)と話す
- 日記を書いたらYouTubeを見る
ただ、注意点として成し遂げたいゴールや目的と矛盾しない報酬(ご褒美行動)と組み合わせなければならない。
例えば以下は適切ではない。
- ダイエットがゴールにもかかわらずジムに行ったらアイスクリームを食べる
- 朝の時間を使いたいのに早起きしたらYouTubeを見る
こうした組み合わせは本来成し遂げたいゴールや目的を阻害するご褒美行動とセットになっているため、適していない。
本来のゴールや目的と敵対しないご褒美行動を設定しよう。
私はこのブログを書くための朝活を以下のように習慣化している。
・朝活をする(習慣化したい行動)ためにカフェに行く(ご褒美行動)
・朝活をしたら手帳に朝活を行った時間(朝活を始めた時間)を記録する
ご褒美行動は習慣化したい行動と同時に行うか、直後に行うことを徹底しよう。
その行動をしたらご褒美である報酬がもらえると行動と報酬を結びつけることが大切だ。
④繰り返しによる固定化(習慣化)
最後は①~③を繰り返すステップである。
繰り返すことで習慣化される。
習慣化されると意志力やモチベーションに頼らなくても行動することが当たり前になる。
逆にやらないと気持ち悪くなる。
そうなれば習慣化され、無意識にもできるようになっていくのだ。
一般的に習慣化には約66日かかると言われれている。
ただ、習慣にしたい行動の負荷や本人の性格、環境によって変動はある。
早寝早起きや運動などの生活リズムを変えていく習慣は3か月以上かかることもあるのだ。
期間に違いはあれど、「きっかけ(トリガー)→行動→報酬」のサイクルを一定回数繰り返すことが習慣化には必要不可欠である。
繰り返しによる固定化(習慣化)とは?

繰り返しによる固定化(習慣化)は「きっかけ(トリガー)→行動→報酬」のサイクルを一定回数繰り返すことである。
①~③の「きっかけ(トリガー)→行動→報酬」は習慣にしやすくなる要素であるが、繰り返さなければ習慣化されない。
改めて、習慣の定義についても触れておくと以下の通りである。
無意識のうちに繰り返される行動のループ
習慣化のメカニズムは脳の記憶とは関係なく、脳が省エネでも行動できるようにすることで起こる。
つまり、習慣化は勝手に起きているのだ。
行動の40%は習慣によって引き起こされている。
最後のプロセス、繰り返しによる固定化(習慣化)にもポイントがあるので見ていこう。
繰り返しによる固定化(習慣化)のポイント
繰り返しによる固定化(習慣化)のポイントは2つある。
・2回はさぼらない
・完璧は目指さない(プランBを用意しておく)
2回はさぼらない

習慣化する上で一番の敵は「やらないこと」である。
だから、シンプルなルールを設ける。
それは「2回はさぼらない」である。
1回目の失敗、やらない日はアクシデントである。
ただ、2回の失敗、やらない日は新しい習慣の始まりになる。
習慣が途切れてしまうことは問題ではない。習慣が途切れ続けることを許してしまうことが問題である。
つまり、1度さぼってしまった次の日や次の機会には必ずやろう。
完璧は目指さない(プランBを用意しておく)
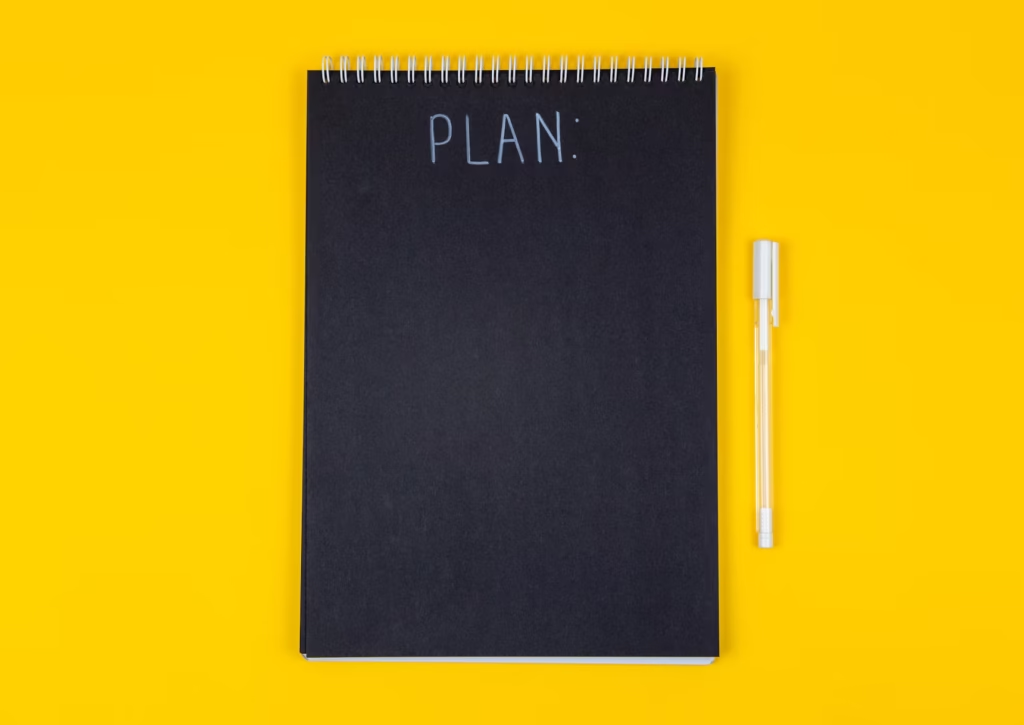
習慣化の上では完璧を目指さないことも大切である。
続ける上でハードルを高くしすぎてしまうとそれがストレスになる。
ストレスになると続かない。
「完璧を目指さない」を具体的に言うとプランBを設けることとも言える。
ステップ②の「行動のスモールステップ化」によって行動を簡単にしたこともここにつながる。
とはいえ、「毎晩寝る前に本を1ページ読む」「毎日、1行だけ日記を書く」は続けるうちにより多くの習慣になっていくはずだ。
その際にプランBを持っておくこと、元々の小さな目標に戻すことが続ける上で重要である。
例えば
- 「毎晩寝る前に本を20ページ読む」を続けていたが、今日は疲れているなと感じた時、「本を1ページだけ読む」というプランB(元々の小さな目標)を実践する
- 「毎日、日記を1000文字程度書く」を続けていたが、今日は忙しくて時間がないと感じた時、「日記を1行だけ書く」というプランB(元々の小さな目標)を実践する
できる時にはプラスアルファの行動をしていけばよいが、「疲れている時」「忙しい時」「調子の悪い日」にプランB(元々の小さな目標)でよしとできるか、成功と思えるかが続ける上で重要なのである。
まとめ
書いていたらこんな大作になってしまった。最後までに見てくれて本当にありがとう。
ただ、本質的な習慣化の仕組みを詰め込んだ。
かなり長い記事になったので確認していこう。
【人生を変える習慣化4Step】
①きっかけ(トリガー)の明確化=習慣を忘れないようにするサイン、習慣(報酬)に気づくこと
きっかけ(トリガー)を明確にするとは「タイミング」と「場所」を決めること
〇タイミング:「○○の習慣(今ある習慣)をした後に△△の習慣(新しい習慣)をする」ことを決めること
〇場所:
・新しい習慣と新しいもの(環境にある特定の場所やもの)を結びつける
・行動を起こしやすい準備がされている
・複数のきっかけがある
②行動のスモールステップ化=行動を簡単にすること、行動しやすくすること
〇環境作り(行動を起こしやすくする準備)
〇2分間ルール:「新しい習慣を始めるときには2分以内にできるものにする」
③報酬の明確化=行動する前に行動したいという欲求を生み出し、行動した後に満足し、また行動したいという欲求を生み出すもの
〇習慣の記録:カレンダーや手帳に習慣を実行した日を印をつけること
〇ご褒美習慣との抱き合わせ:「自分がしたい行動(ご褒美行動)」と「しなければならない行動(習慣化したい行動)」をセットにすること
④繰り返しによる固定化(習慣化)=「きっかけ(トリガー)→行動→報酬」のサイクルを一定回数繰り返すこと
〇2回はさぼらない:1回目のさぼりは許すが2連続のさぼりは許さない
〇完璧は目指さない(プランBを用意しておく):プランBを持っておくこと、元々の小さな目標に戻すこと
多かれ少なかれ、習慣化できている行動にはこの4Stepを必ず満たしている。
つまり、この習慣化4Stepを活用すれば習慣を作り出せることができるのだ。
人生は習慣によってできている。
そして、人間の4割以上は習慣によって成り立っている。
習慣を意図的に作り出せることができれば、人生は変わる。
人生を思い通りにデザインすることができる。
知識やノウハウだけあっても意味がない。
人生を変えるために大切なのは行動であり、習慣である。
ここまで記事を読めたあなたには続ける才能がある。
物事を進めていく強い信念を持っている。
迷ったときには二つの選択肢がある。
やるか、すぐやるか
見てくれているあなたの人生、習慣が少しでもより良くなることを願って。

最後までご覧いただきありがとうございます。
ブログの内容を動画にまとめてYouTubeにUPしています。
見ていただけると幸いです。
https://www.youtube.com/@habituation-laboratory